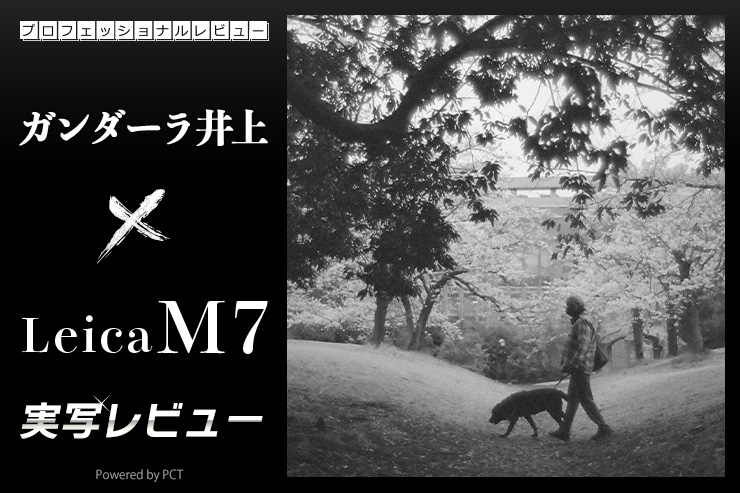
はじめに
Leica M7の基本仕様について
シャッターダイヤルにAUTOの表記
あっさりした印象のカメラ背面
電源は6Vで駆動される仕様
フィルム交換は底蓋を外して行う
フィルム圧板がパカっと起き上がる
Leica M7にフィルムを通す
試写作例その1
試写作例その2
試写作例その3
まとめ

ライター。1964年 東京・日本橋生まれ。早稲田大学社会科学部卒業後、松下電器(現パナソニック)宣伝事業部に13年間勤める。2002年に独立し、「monoマガジン」「BRUTUS」「Pen」「ENGINE」などの雑誌やwebの世界を泳ぎ回る。初めてのLeicaは幼馴染の父上が所蔵する膨大なコレクションから譲り受けたLeica M4とLeica ズマロン 35mm F2.8。著作『人生に必要な30の腕時計』(岩波書店)、『ツァイス&フォクトレンダーの作り方』(玄光社)など。編集企画と主筆を務めた『Leica M11 Book』(玄光社)も発売中。
この記事を書くことになったきっかけは「ガンダーラさん、現在Leica M7の実機はお持ちでしょうか?」という1本のメールでした。何台かあるM型Leicaのうち、Leica M7に関しては入手して以来ずっと手元にあり、自分にとってフィルム機のLeicaでは稼働率の高い実用機という位置付けです。そんなわけで今回はごく個人的な視点でLeica M7の印象と作例を紹介することになりましたのでお付き合いのほどよろしくお願いします。
まずはLeica M7の基本仕様を確認しておきましょう。Leica M7は35mm判フルサイズ(いわゆるLeica判)の撮影フォーマットで135フィルムを用いるアナログのレンジファインダーシステムカメラです。レンズマウントはLeica Mシステムで、1954年に登場したLeica M3から現在のデジタルMシステムまで継承されているもの。フォーカシングはマニュアル専用で、フィルム巻き上げはレバー式でフィルム巻き戻しはクランク式の手動が基本。オプションで巻き上げに関しては電動化することも可能です。露出決定はLeica M6と同様のマニュアル式に加え、絞り優先オートでの撮影も可能です。
Leica M7の最大の特長は、実絞りでオートが効くこと。シャッターダイヤルをAUTOの位置にしてやれば、設定された絞り値に応じた適正露出となるシャッター速度をカメラが決めてくれます。シャッター速度はファインダーの下部に赤い7セグメントのLEDで数字が浮かび上がる仕立て。要するにLeica M8以降のMデジタルが継承しているインターフェイスはLeica M7を起源とするとも言えます。だから、M型Leicaはデジタル機しか使ったことのない方にもLeica M7は使いやすいモデルだと思います。
デジカメを見慣れた目からすると、カメラの背面はスッキリしています。液晶モニターもファンクションボタンも何もなくて、ファインダーの覗き窓とフィルム感度の設定ディスクがあるだけです。装填したフィルムのISO値をディスク3時位置の指標に合わせる、あるいはDXコードのついたパトローネのフィルムであればDX表記を指標に合わせれば自動設定も可能。シャッターボタン外周のメインスイッチを操作して電源を投入するとファインダー内に感度の数値が短時間表示されます。9時位置のボタンを押しながらディスクを回転させて露出補正をかけることも可能。アナログ表記なので見落としが防げる素晴らしいインターフェイス設計だと思います。
Leica M7は露出計の作動に加えて、シャッター後幕を繋止・走行させるために電磁制御を用いていることから6Vの電源を必要とします。1970年代の国産電磁制御シャッターも6V仕様で4SR44積層電池とかを使っていたものでしたが、本機の場合はCR1/3という3Vのリチウム電池を2本装填するのが推奨される使い方です。これは今となっては入手が難しい電池なので旅先などで電池が上がった場合にはSR44酸化銀電池もしくはLR44アルカリ電池を4発装填するという緊急対応も裏技として覚えておくといいかもです。ちなみに電池がなくても1/60秒と1/125秒の2速だけは機械制御でシャッターを切ることができます。
ボディの斜め下方向から見るとこんな感じ。左にパトローネを入れて、巻き上げレバー直下にある3つのスリットのうちどれか1つにフィルムの先端を挿入してね。というグラフィックガイドが底蓋を取り外すと見えます。イラストガイドの右にある銀色のパーツは底蓋側からフィルム巻き上げをするためのカップリング機構で、ここにLeicaモーターとかLeicaビットが連結できるのですが、正直あまりその作動の感触は心地よいものではないなぁ。というのが個人的な感想で、巻き上げレバーを使う方が楽しいカメラです。
これはLeica M3以来の伝統的な仕立てなのですが、フィルム圧板部分が蝶番でパカっと起き上がるので、フィルム装填する時にスプロケットの爪にフィルムのパーフォレーションがしっかり噛み合っているのかどうかを確認できます。Leica M7ではこの裏蓋にフィルム感度設定ディスクがあるので、その情報を伝えるための金メッキされた接点3つがアパーチュア側にもあります。ここの接触が悪くなると露出関係のトラブルの元になりかねませんので汚さないように注意したいものです。
久しぶりにLeica M7を使うので、念の為に電池を入手しておきました。機械式で緊急シャッターを使う場合には前述のとおり1/60秒と1/125秒しか選択の余地がないので、日中の光線では絞りを開けてピントを浅くした写真は撮れなくなるのでその予防の意味もあります。今回は、新旧3本のレンズで撮影してみることにしました。
まずは最近のLeica Mマウント互換でコンパクトなサイズ感が特長のフォクトレンダー ヘリアー40mm F2.8 AsphericalをLeica M7につけて持ち出します。このレンズ、見た目は大昔のレンジファインダー用ニッコールっぽい雰囲気でヴィンテージ感むんむんですが非球面レンズ搭載なので写りはキレッキレになることが期待できる現行品です。フィルムはKodakのColor Plus 200カラーネガを装填。C41の現像処理のあと16BASEでスキャンしてもらったJPGデータをもとに、GIMPですこしトーンの調整をしています。
Leica M7・フォクトレンダー ヘリアー 40mm F2.8 Aspherical・絞り優先オート(絞りF5.6・1/250秒)・Kodak Color Plus 200
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
清洲橋を渡っていたら、松本零士先生がデザインした水上バスの第3世代エメラルダス号を発見! このレンズを装着してもファインダーフレームは50mmが出ているので、そこからはみ出たタイミングで撮ったらバッチリでした。こういうとき絞り優先オートだとフレーミングに集中できますね。
Leica M7・フォクトレンダー ヘリアー 40mm F2.8 Aspherical・絞り優先オート(絞りF2.8・1/125秒)・Kodak Color Plus 200
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
40mmは準広角ですが、F2.8の絞り開放にすれば背景は程よくボケてポートレートもいい感じに撮れます。モデルはコロナ禍中の大病からリハビリを経て奇跡の復活を遂げた合同会社PCT(元日本カメラ編集長)のS木さん。元気な姿を見られて本当に嬉しかったです!
Leica M7・フォクトレンダー ヘリアー 40mm F2.8Aspherical・絞り優先オート(絞りF11・6秒)・Kodak Color Plus 200
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
隅田川にかかる橋梁にはライトアップされているものが多いのですが、蔵前橋では橋の下側の構造が見えるように照らしているんですね。欄干にLeica M7を押し付けて絞りF11でオート撮影。長時間露光オート撮影ができるフィルム機のM型LeicaはM7だけです。
つづいて登場するのはLeica M7と同時代の広角レンズ、Leica エルマリートM f2.8/21mmです。Leica M7はレンズからの光をシャッター幕の白い丸に反射させて測光する構造なので、バックフォーカスの長いレンズでないと正確に測光できません。このことから本レンズは一眼レフに用いられたことで知られるレトロフォーカスタイプのレンズ構成で、前玉に立派な凹レンズが用いられていて迫力があります。フィルムはILFORD XP2 super 400を装填。C41の現像処理のあと16BASEでスキャンしてもらったJPGデータをもとに、GIMPですこしトーンの調整をしています。
Leica M7・Leica エルマリートM f2.8/21mm・絞り優先オート(絞りF11・1/500秒)・ILFORD XP2 super 400
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
例年よりゆっくりしたタイミングで開花した桜の樹を見上げるアングル。対角線でおよそ90度の画角は、肉眼とは異なるパースペクティブで眼前の光景を捉えます。ネガフィルムの光の許容度の高さから、桜の花びらもちゃんと見えていますし画面周辺までしっかり結像しています。
Leica M7・Leica エルマリートM f2.8/21mm・絞り優先オート(絞りF4・1/125秒)・ILFORD XP2 super 400
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
いわゆる超広角レンズの作り出す世界は、極端なパースペクティブが魅力なのだと思います。ちょっとアングルを変えただけで目まぐるしく構図が動いていく様子を光学式の小さな外付けファインダーで覗き込みながら撮影するのはやっぱり楽しいですね。
Leica M7・Leica エルマリートM f2.8/21mm・絞り優先オート(絞りF8・1/250秒)・ILFORD XP2 super 400
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
レトロフォーカスタイプで非球面レンズも採用されていないと聞けばそれなりの画質なのかと思いがちですが、このレンズは違います。スペースシャトルのオービターっぽい意匠の植栽にググッと近づいて撮影しましたが、主翼も尾翼もまっすぐで歪曲収差をまったく感じさせない優秀さです。
最後の1本は、Leica M7登場以前の1960年代に光学設計されたLeica ズミルックスM f1.4/35mmにしました。最近Leicaが最初機バージョンの復刻版を新製品としてリリースしましたが、このレンズはM型Leicaに装着した姿の格好良さではピカイチだと思います。写りに関しては絞り開放で盛大にフレアが出たりします。そこでビンテージっぽさを強調すべくフィルムはフジの廃盤プロ400カラーネガ(期限はなんと2010年!)を装填。感度劣化を鑑みてプラス1段の露光で撮影してC41の現像処理のあと16BASEでスキャンしてもらったJPGデータをもとに、GIMPでモノクロ化してトーンの調整をしています。
Leica M7・Leica ズミルックスM f1.4/35mm (2nd)・絞り優先オート(絞りF1.4・1/250秒)・フジカラーPRO400・+1EV補正
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
絞りは開放のF1.4で絞り優先オートにして撮影。逆光になる樹木のエッジ部分に光のヴェールをまとった様なフレアが発生しているのがお分かりになるでしょうか? この絞り開放での描写が面白くて大好きという人とグダグダに感じて嫌いという両極端な評価を生み出します。
Leica M7・Leica ズミルックスM f1.4/35mm (2nd)・絞り優先オート(絞りF1.4・1/500秒)・フジカラーPRO400・+1EV補正
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
個人的にはLeica ズミルックスM f1.4/35mmの絞り開放の描写は大好物です。3週間前に撮影したのに30年前みたいな写真が撮れる、まるでタイムマシンの様なレンズだと思います。
Leica M7・Leica ズミルックスM f1.4/35mm (2nd)・絞り優先オート(絞りF5.6・1/125秒)・フジカラーPRO400・+1EV補正
画像にマウスを合わせると拡大表示します
画像をスワイプすると拡大表示します
Leica ズミルックスM f1.4/35mmの名誉のために申し上げるなら、何段階か絞れば極めて優秀で安心できる描写の広角レンズとして働いてくれます。F5.6ではこのとおり。黒いタイヤの中にあるトーンの豊富さもいい感じです。
M型Leica初の電磁制御式シャッターを搭載することで、絞り優先オート撮影を可能とするLeica M7が登場したのは2002年のこと。機構的には電磁制御とはいえバルナック型Leica以来の伝統的な3軸横走行シャッターを採用しているので、巻き上げやレリーズの操作感覚はアナログのLeica M型そのものでありながら、露出の決定に手間取らないのが魅力です。今回は新旧のLeica Mマウントレンズで撮影を楽しみました。特に古い設計のレンズではデジタル機に装着した場合よりも素直な雰囲気の写真が撮れる気がします。そのような意味でも、Leica M7はフィルムでMマウントレンズ各種の描写を味わうのに好適なボディだと思います。